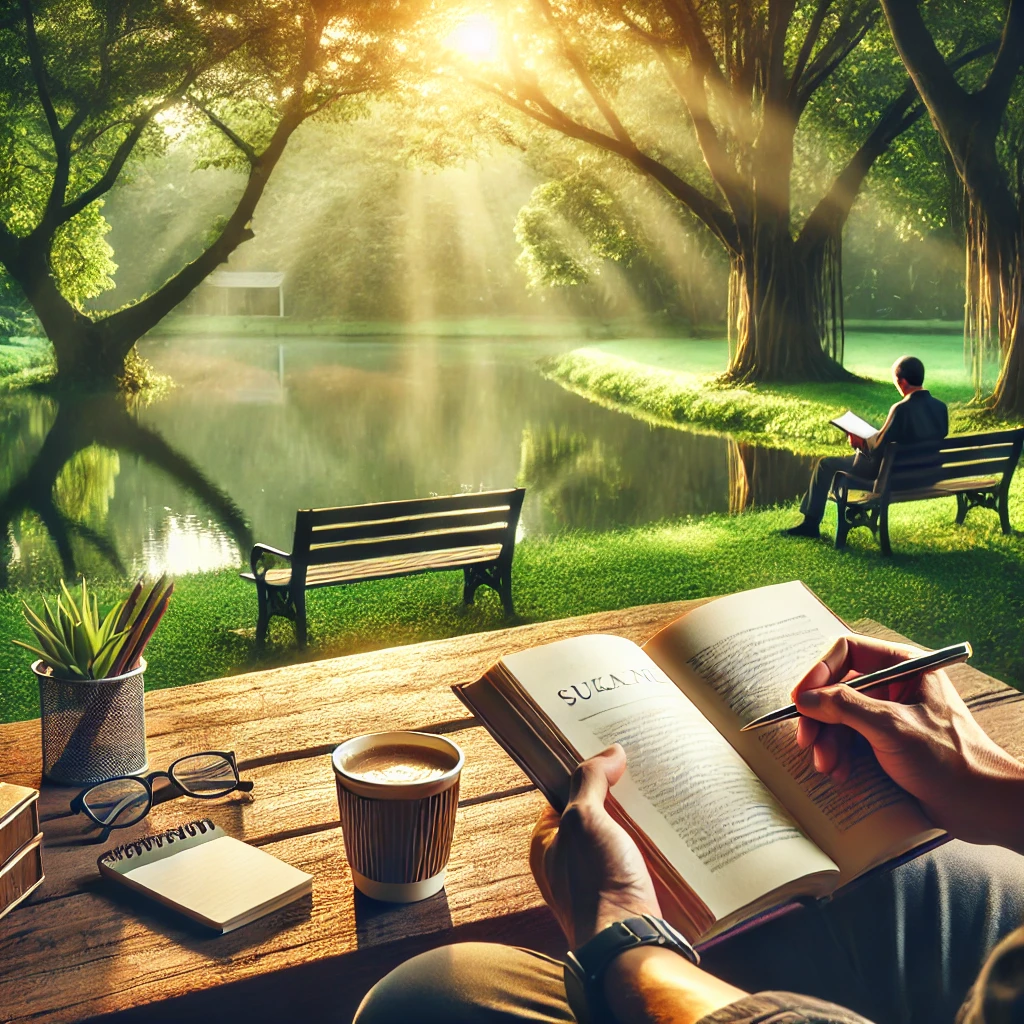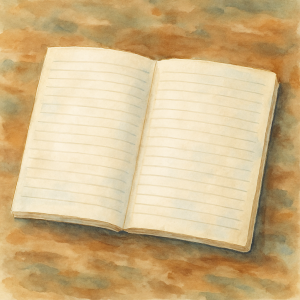寓話
京に住む蛙はかねてから大阪見物をしたいと思っていた。春になって思い立ち、街道を西向きに歩いて天王山に登った。
大阪に住む蛙はかねてから京見物をしたいと思っていた。同じ頃、思い立ち、街道を東向きに歩いて天王山に登った。
京の蛙と大阪の蛙は頂上でばったりと出逢った。互いに自分の願いを語り合った後、「このような苦しい思いをしてもまだ道半ばだ。この分では彼の地に着いた頃には足腰が立たないようになるだろう。ここが有名な天王山の頂上で、京も大阪も一目で見渡せる場所だ。
お互いに足をつま立てて背伸びをしてみたら、足の痛さも和らぐだろう」。両方の蛙が立ち上がり、足をつま立てて向こうを見た。 京の蛙は「噂に聞いた難波の名所も、見てみれば何ら京と変わらない。しんどい思いをして大阪に行くよりも、これからすぐに帰ろう」と言った。大阪の蛙は「花の都と噂に聞いたが、大阪と少しも違わぬ。おれも大阪に帰る」と言い残し、のこのこと帰った。両方の蛙は向こうを見た心づもりであったが、実は目の玉が背中についているので結局は古里を見ていたのだ。
引用元:座右の寓話 戸田智弘 出版社 ディスカヴァー・トゥエンティワン
www.amazon.co.jp/dp/47993282
感想と教訓
あらすじ
京都と大阪のカエルがそれぞれ相手の町を見物しようと旅に出ますが、山の頂上で出会い、背伸びして町を見ようとします。しかしカエルの目は頭の上や背中側についているため、実際には自分が来た方、つまり自分の故郷を見てしまいます。それに気づかず、「相手の町も自分の町と同じだ」と思い込み、旅をやめて帰ってしまいます。
自分の立場を客観視する
この寓話からの教訓として、自分を客観視することの重要性が読み取れます。自分がどういう立場や境遇にあって、それを前提として考え方の偏りや重視していることを、普段から俯瞰して考えておくことが重要であるといえます。
一例ですが、私は普段の業務によって以下のような視点を持っています。
公認会計士:上場企業の決算開示業務として、効率的かつ重大なミスなく業務が遂行できる仕組みが重要という視点
税理士:正確な判断のために、事実関係を正確に捉えるという視点
中小企業診断士:不確実な状況下で限られた情報でも意思決定をしてアクションを実行する必要があるという視点
どれか1つの視点だけで臨んでしまうと、他のものが重視される際に付加価値を出せないことがあり得ます。もちろん自分で責任をとる必要がある場面ではその役割に応じた考えを重視せざるを得ませんが、別の観点からアイデアを出すことが必要になることもあるため、その時々の状況を俯瞰して捉えるよう心掛けています。
一次情報と行動の大切さ
また、思い込みに囚われず、正確な一次情報を自分の眼でみることの重要性も教訓として見出すことができます。カエルは遠目には自分の町と変わらない、と引き返してしまったわけですが、実際に行ってみれば誤解に気づくことができました。
現実には時間や体力、お金などのリソースは有限であるため、無駄な行動はとりたくない、という考え方もあるかもしれません。しかし、そう考える人が多いがゆえに、他の人が引き返す場面で労を惜しまずにもう少しだけ進んでみると、思いもよらぬ機会に恵まれることもあり得ます。リスク管理やリソースの余裕を踏まえて判断しましょう。
経営学には深化と探索という考え方があります。深化は既存の得意な領域を深堀すること、探索は普段取り組んでいない新たな領域へ踏み込んでいくことをいい、これを両輪で回すことがイノベーションを起こすために必要であるという考え方です。探索の場面では、多少は効率を度外視して踏み込んでみると、新たな発見があるかもしれません。